さぁ、年末です!
「神さまに失礼の無いように、神さまに喜んでいただく」ことを判断基準にして大掃除をいたしましょう!
一年間のご守護と後押しに感謝を込めて、神さまが居心地よくおられるように、神棚の周辺を聖域として本格的に清めます。
今このページをご覧のあなたは、もしかして、おうちに神棚をまつり、初めての年末をお迎えでしょうか?
さて…年末が来たけれど…
「年末の大掃除の仕方は一体どうすればいいの?!わからない!」と、思っていらっしゃるかもしれませんね。
大丈夫です!
順を追って、これだけは絶対に外せないという部分と、やった方がいいよ♪な推奨部分とをしっかりお伝えしますので、ご参考になさってみてくださいね。^^
御神札のおまつりから大掃除完了までの流れ
我が家では、毎年末に旧い御神札(おふだ)をお受けした神社にお納めし、新しい御神札をお受けして来てまつります。
流れはザックリと下記のような流れです。
御神札は初詣でお受けするのだけど?という場合
「御神札は年末じゃなくて、初詣でお受けするんですが。」という方も多くいらっしゃるでしょう。
それもまた、正しきことです。
「日頃信仰している神社の御神札を毎年正月新しくお受けしてまつる。」
神社で頂戴した神社暦には、上記のように記載されてあります。(2019.1.11)
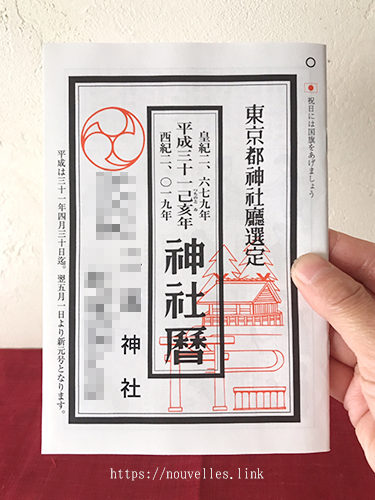
その場合には、大掃除を終えてから初詣に伺うまで、一旦お宮にお入りいただく形で構わないでしょう。
chino家の場合は、旦那の産土神社が現住まいから遠いので、頻繁にうかがうことも叶わず、年末にお受けしています。
年末の神棚の大掃除は13日から28日までに!
12月13日頃に行われるすす払いが一年の煤と邪気を祓い、1年の福を司る年神さまをお迎えする「正月」の準備を始める正月事始めです。
余裕のある方は、この日あたりから神棚の掃除に取り掛かるとよいでしょう。
できれば、28日までには大掃除を済ませたいですね。
年末は、神棚におられる神さまと、年神さま(お正月さま)もお越しです。
12月29日(苦立て・二重苦)と31日(一夜飾り)を避けて年神さまをお迎えするための門松や鏡餅、などのお正月の飾りつけをします。
年神さまはキレイ好きですので、お迎えするまでに大掃除を済ませておきましょう。

汚部屋だと年神さまは帰っちゃうよ!
それでは、御神札のまつり方から、大掃除完了までを順番にご説明いたしましょう。
一年間の感謝をお伝えして御神札を抜く
まず、新しい御神札をお受けする前に(大掃除の前に)今までの御神札に1年間ご守護・後押しいただいた感謝をお伝えしましょう。
御神札をお宮から抜く前に、いつものお供え(米・水・塩)と御神酒を供え、感謝をお伝えします。
「今まで、大いなるご守護と後押しをいただき、誠にありがとうございました!」
しっかりと感謝をお伝えしたら、「失礼します。」と一声おかけして、お宮の御扉を開きます。
御神札を抜く際には、御神札に息が直接かかって御神札が穢れないように、マスク(もしくは口に半紙などの紙を挟む)をします。

人間の息は、けがれなのね。
神棚がきちんと機能しているかどうか、ここでわかります!
お宮の御扉を開いて御神札を抜くとき、日々のお参りがきちんとされていたかチェックできます。
御神札を手にしてみた時、どうでしょうか?
御神札からほわぁっと温かさを感じられたら、その御神札にはちゃんとパワーがありご神霊が宿っていますよ。

日々のお祈りがきちんと神さまに通じている場合には御神札が温かいのです。^^
もしも、御神札がひんやりと冷たく感じられた場合には、お祈り(神さまとのコミュニケーション)が足りていません。
祈り=(意乗り)が通じるようにしっかりと心をこめて日々のお祈りをいたしましょうね。
また、お祈りをすると、合掌した手がビリビリとしたり、真っ赤になったり、ホカホカと暖かくなっていたり、お腹がホカホカとしていたら、きちんと神さまにお祈りが通じています♪
御神札をお宮から抜いたら、白い紙に包んで神社に納めに参り、新しい御神札をお受けします。
御神札を新たにするタイミングで神棚も新たにするのもグッドですね♪
御神札を神社にお納めに伺い、新しい御神札をお受けする

御神札をお納めするにあたり、拝殿で「一年間、大いなるご守護・後押しを誠にありがとうございました。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします!」とお伝えした後、御神札を古神符納札所に納めます。
年末の神棚の本格的なお掃除
さぁいよいよ、新しい御神札をおまつりする前の清掃です。
神道は祓い清めに始まり、祓い清めで終わります。
神さまは何よりも穢れ(気枯れ・汚れ)を嫌いますので。
まず、神棚のあるお部屋を清めてから、神棚のお掃除に入ります。
その前に自分自身も祓い清めておきましょう。
通常、神社の手水同様に手と口をすすぎますが、粗塩と清酒を入れたお風呂で全身を清めると、なお、よろしいですね。^^

身も心もピカピカに♪
用意するもの
- 神棚専用に新しいフキン(タオル) 2枚(水拭き用と乾拭き用)
- 粗塩(フライパンで炒った天然塩が良い)
粗塩はフライパンでカラカラに炒った粗塩を用意すると、なお良しです。
なぜならば、火(カ)と水(ミ)で神(かみ)になるからです。
神棚の本格的お掃除の手順
神域となる神棚の前では、神社での手水での清めと同様に手と口をすすぎ、穢れや邪気を祓い清めます。
「これからお掃除いたします。もしもご無礼がありましたらお許しください。失礼いたします。」
と、お部屋全体に一声お声掛けします。
粗塩をパラパラと床にまき、しばらく置き、塩に邪気を吸ってもらいます。
絨毯の場合は塩はまかずに、先に部屋の四隅に盛塩を置き、塩に邪気を吸っておいてもらいます。
禊祓詞(みそぎはらえのことば)を奏上し場を清めます。
※必須ではなく、やるとなお良いという推奨項目です。
【禊祓詞(みそぎはらえのことば)】
高天原(たかまのはら)に神(かむ)づまり坐(ま)す 神魯岐(かむろぎ) 神魯美(かむろみ)の命(みこと)もちて 皇御祖神(すめみおやかむ) 伊邪那岐大神(いざなぎのおほかみ)筑紫(つくし)の日向(ひむか)の橘の小門(おど)の阿波岐原(あはぎはら)に 禊祓い給ひし(みそぎはらひたまひし)時に 生れ坐せる(あれませる)祓戸(はらへど)の大神等(おほかみたち) 諸々の禍事罪穢れ(まがごとつみけがれ)あらむをば 祓へ給ひ清め給へと白(まお)す事の由(よし)を 天津神(あまつかみ)国津神(くにつかみ)八百万神等共(やおよろずのかみたちとも)に 聞食(きこしめ)せと恐(かしこ)み恐(かしこ)みも白(まお)す
とってもありがたい祓戸の大神、祓ひ給え清め給へ
神棚にまつっている神具を、机や台の上に丁寧に降ろします。

このとき、マスクや半紙を口に挟むなどしてお宮に息がかからないようにしましょう。
人間より上位である神さまのお住まいであるお宮や神具類を、人間が立っている床に置きません。
やむおえず床に置く場合には、白い紙などを敷きその上に置きます。

※chino家の神棚の場合は、壁掛け式の箱宮ですので御扉のみを外します。

神棚専用のキレイなフキンに水気を固くきっちり絞った雑巾で水拭きします。

カビが発生しないように、しっかりとすべて丁寧に拭き上げたら、最後に乾拭きで丹念に拭き上げます。
元の通りにお宮を戻し、神棚に神具類を戻し整えます。
床にまいた塩を始末した後、雑巾で水拭きと乾拭きをします。

新しい御神札は新しいご神気に満ちていてホワッと温かいです!^^

お供え(米、酒・塩・水)をお供えします。
御扉を開けたまま、神棚拝詞を奏上します。
※通常は御扉は閉めておきます。
【神棚拝詞(かみだなはいし)】
此(こ)れの神床(かむどこ)に坐(ま)す 掛(か)けまくも畏(かしこ)き 天照大御神(あまてらすおおみかみ) 産土大神等(うぶすなのおおかみたち)の大前を拝(おろが)み奉(まつ)りて 恐(かしこ)み恐(かしこ)みも白(まお)さく 大神等(おおかみたち)の広き厚き御恵(みめぐみ)を辱(かたじけな)み奉(まつ)り 高き尊き神教(みおしえ)のまにまに 直き正しき真心もちて 誠の道に違(たが)うことなく 負ひ持つ業(わざ)に励ましめ給ひ 家門(いえかど)高く 身健やかに 世のため人のために尽さしめ給へと 恐(かしこ)み恐(かしこ)みも白(まお)す

chino家の猫も神さまのお部屋(神棚のある部屋をそう呼んでいます)が大好き。

祝詞を神妙に聞いてるね♪
chinoちゃんは、祝詞のCDをスマホで流します。
神棚にはまだ神さまはおられませんが、神さまのお住まいであるお宮とお部屋全体を浄める・お部屋に聞かせする意図で流します。
同時にお香を炊きます。
清めるためになんでもやる!という気持ちです。
普段の掃除中もお香を炊き、祝詞のCDをかけて、祓い清めパワーを倍増させています。^^
※実際に愛聴しているCDは産土祝詞なども収録されているCDでご紹介しているものとは別のものです。
普段のお掃除はこちらも参考にどうぞ▼
今年のお礼、今年のうちに!!
「今年の汚れ、今年のうちに」
というCMがあったのをご存じの方はいらっしゃいますか?^^
神さまへのお礼も、できれば年内に感謝をお伝えし、スッキリとした気持ちで新しい年をお迎えしましょう♪
「初詣よりも年末参りにうかがって、神さまに1年間の感謝をお伝えしたほうがいいですよ!」
と、ある方から教わって10年以上経ちます。
初詣は普段は神社に行かれない方、1年の内初詣しか参拝されない方も多くいらっしゃって混雑しますし、落ち着いて祈れないので、確かにゆっくりと神さまに向き合えるのは年末の方がよいと思い、それ以来は年末参りを欠かしません。
初詣も、三が日以内にしなくてはいけないというものでもありません。
何も混雑している時に行かなくてもいいのです。
年末参りをchinoちゃんはオススメします。^^
おわりに
おうちに神棚をまつって初めての年末だけど…
・年末の大掃除の仕方は一体どうすればいいの?!わからない!
という方のために、chinoちゃんちの大掃除の仕方などをお伝えいたしました。
年末の大掃除で穢れを一掃し、新しい御神札と共に、新しい一年をパワフルにお迎えしていただければ幸いです。
あなたにたくさんの福がありますように…♪






